カンピロバクター食中毒について
カンピロバクター食中毒の発生件数は、1996年まで年間20~30件で推移していましたが、1997年ころから増加傾向に転じ、患者数1名の食中毒も件数に計上するようになったため、最近5年間では、年に300件から500件台で推移しています(表1参照)。この食中毒は、現在ノロウイルス食中毒に次いで発生件数が多く、原因食品としては、鶏肉が最も重要視され、食中毒患者への喫食調査から生鶏肉(鶏わさ、刺身、鶏レバー)、加熱不十分な食品(湯通しササミ、鉄板焼き、バーベキュー、ちゃんこ風鍋料理)、サラダ、飲料水などが報告されています。
(表1) カンピロバクター食中毒の発生状況(厚生労働省全国食中毒統計)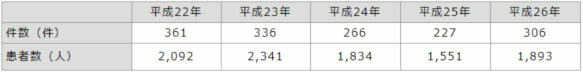
カンピロバクター属菌の特徴
カンピロパクター(Campylobacter)属菌は、現在、17菌種6亜種3生物型に分類されています。これらのうち1982年に厚生労働省はC. jejuni/coli(ジェジュニー/コリー)の2菌種を食中毒起因菌として例示しており、食中毒患者からはC. jejuniが高率に分離されます。海外では、C. upsaliensisが胃腸炎患者から分離され、その病原性も認められていますが、我が国では患者の発生が報告されていません。 C. jejuni/coliは、家畜、家禽、ペット、野生動物、野鳥等あらゆる動物の腸管に広く分布しています。保菌率は、牛で数~40%、鶏で50~80%であり、ほとんどがC. jejuniです。また、ブ夕では、C. jejuniよりC. coliが多く検出されています。 C. jejuni/coliは、30〜45℃及び微好気性(わずかな酸素が有るところ)の環境下で良く増殖し、S字状をした螺旋状の桿菌(写真1参照)のために、特有のコルクスクリュー様運動をします。食中毒を起こす菌量は、数百個程度で、少量菌を食品とともに経口的に摂食することで発症します。

(写真1)カンピロバクター電子顕微鏡写真
(食品安全委員会事務局資料)
カンピロバクター食中毒の症状
潜伏期は、感染菌量により2~7日(平均3~4日)で、比較的長いのが特徴です。 腹痛(長期間継続)、下痢(1日10回以上2~3日)、発熱(38℃以下)が主症状で通常、 発熱、倦怠感、頭痛、筋肉痛等の後に吐き気、腹痛が見られます。
カンピロバクター食中毒の予防
● 食肉を取り扱った後は、十分に手指を洗浄・消毒すること。
● 食肉の生食を避け、十分加熱して食べること。
● 熱や乾燥に弱いので、調理器具は使用後によく洗浄し、熱湯消毒・乾燥すること。
● 生で食べるサラダなどの食品への二次汚染を防止すること。
● 未殺菌の飲料水(井戸水、沢水)を飲まない。必ず塩素消毒や煮沸消毒をすること。
● 動物からの感染に注意すること。濃厚な接触は避け、接触後は必ず手を洗うこと。
