黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)食中毒について
黄色ブドウ球菌食中毒は、近年その発生数は減少しましたが、平成12年6月、開西地区を中心に、低脂肪乳などの加工乳を飲んだ人達が次々と嘔吐・吐き気を訴える食中毒が発生しました。この食中毒の原因菌が黄色ブドウ球菌で最終的には患者数が13,420名となり、国内の戦後最大の食中毒となりました。
菌の特徴
本菌は、直径約1μm(1mmの1000分の1)の青く染まったグラム陽性球菌で、表面に存在する粘液性物質によって集まりブドウの房のように見えます(写真1)。また、卵黄加マンニット食塩寒天培地上では黄色い集落を形成し、集落の周りには卵黄反応が見られます(写真2)。これらのことから黄色ブドウ球菌と呼ばれています。なお、本菌は、人や動物の化膿性疾患に関連しており、乾燥に強く、食塩濃度が高い(7~10%)状態でも発育できるという特徴があり、健康な人でも約30%の人の鼻腔や手指などから分離されます。また、毒素型の食中毒起因菌としてもよく知られています。
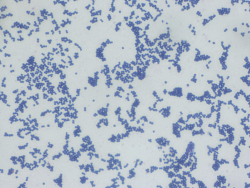
【写真1】
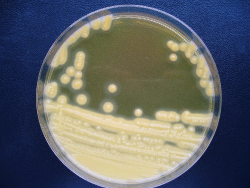
【写真2】
食中毒の原因食品
わが国では、穀類及びその加工食品(おにぎり、弁当、サンドイッチ、ケーキなど)を原因食品とする食中毒が非常に多く、おにぎりによる食中毒が全体の約4割を占めています。主に、調理あるいは製造を素手で行う食品が原因食品として報告されています。
食中毒の症状および発生機序
食品中で本菌が増殖すると、そこにエンテロトキシン(以下、毒素という)が産生されます。この毒素が産生された食品を食べると、1~6時間(平均2~3時間)後に吐き気・嘔吐・腹痛・下痢などの症状が現れます。症状が重篤になることは少なく、数時間から2日で症状は改善します。なお、毒素は、酸に強いため、胃酸でも消化されず、胃や小腸から吸収されて胃腸炎症状を引き起こします。さらに、菌自体は熱に弱く、通常の加熱処理で死滅しますが、毒素は熱にも強く100℃30分間の加熱でも不活化されることはありません。したがって、一旦食品中に毒素が産生されてしまうと、その後、食品を加熱しても毒素は残ります。現在、黄色ブドウ球菌が産生する毒素は、抗原性の違いにより主にA~E型の5種類に分けられ、わが国で発生する食中毒の80~90%はA型毒素産生性黄色ブドウ球菌によって起っています。
予防のポイント
● 手指に切り傷や化膿巣のある人は、食品に直接触れたり、調理をしたりしないこと。
● 手指の洗浄・消毒を十分に行うこと。
● 食品は10℃以下で冷蔵保存し、菌の増殖を防ぐこと。
● 調理にあたっては、帽子、マスク、手袋などを利用すること。
● 食品はなるべく早く食べること。
